テーマ:for文を使い、range()を徹底理解しよう!
rangeとは
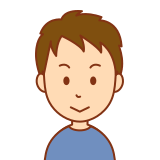
range()はPythonで連続した数値を生成するための便利な関数です。主にfor文で使用され、指定した範囲の数値を順番に処理することができます。
例えば以下のように使います。
[code lang=”python”]
for i in range(5):
print(i)
[/code]
この場合、0から4までの数値が順番に表示されます。
for文×rangeの基本活用例
基本的な使い方
# range()の基本的な使い方は以下の形式です。
[code lang=”python”]
for i in range(start, stop, step):
print(i)
[/code]
# 以下に例を示します。
[code lang=”python”]
for i in range(2, 10, 2):
print(i)
[/code]
# 実行結果
[code lang=”plain” gutter=”false”]
2
4
6
8
[/code]
負の数を扱う
range()は負の数を扱うこともできます。逆方向にカウントする例を見てみましょう。
[code lang=”python”]
for i in range(10, 0, -2):
print(i)
[/code]
# 実行結果
[code lang=”plain” gutter=”false”]
10
8
6
4
2
[/code]
実行結果:
リストのインデックスを使う
リストのインデックスを指定して処理を行う場合、range()を使うと便利です。
[code lang=”python”]
fruits = ['apple' , 'banana', 'orange']
for i in range(len(fruits)):
print(f'{i}: {fruits[i]}')
[/code]
# 実行結果
[code lang=”plain” gutter=”false”]
0: りんご
1: バナナ
2: みかん
[/code]
応用編:条件付きrange
range()は条件付きで柔軟に使うこともできます。以下の例では、偶数だけを処理する方法を示しています。
[code lang=”python”]
for i in range(0, 10, 2):
if i % 2 == 0:
print(i)
[/code]
# 実行結果
[code lang=”plain” gutter=”false”]
0
2
4
6
8
[/code]
リスト内包表記×range
リスト内包表記を使えば、range()で生成した数値を簡単にリストに格納できます。
[code lang=”python”]
squares = [i ** 2 for i in range(5)]
print(squares)
[/code]
# 実行結果
[code lang=”plain” gutter=”false”]
0
4
9
16
[/code]
まとめ
range()はPythonのfor文と非常に親和性が高い機能であり、幅広い用途で利用することができます。基本の使い方から応用まで理解すれば、効率的な反復処理が可能になります。
次回は「セット編」について、Pythonのfor文を活用する方法を解説していきます!




コメント